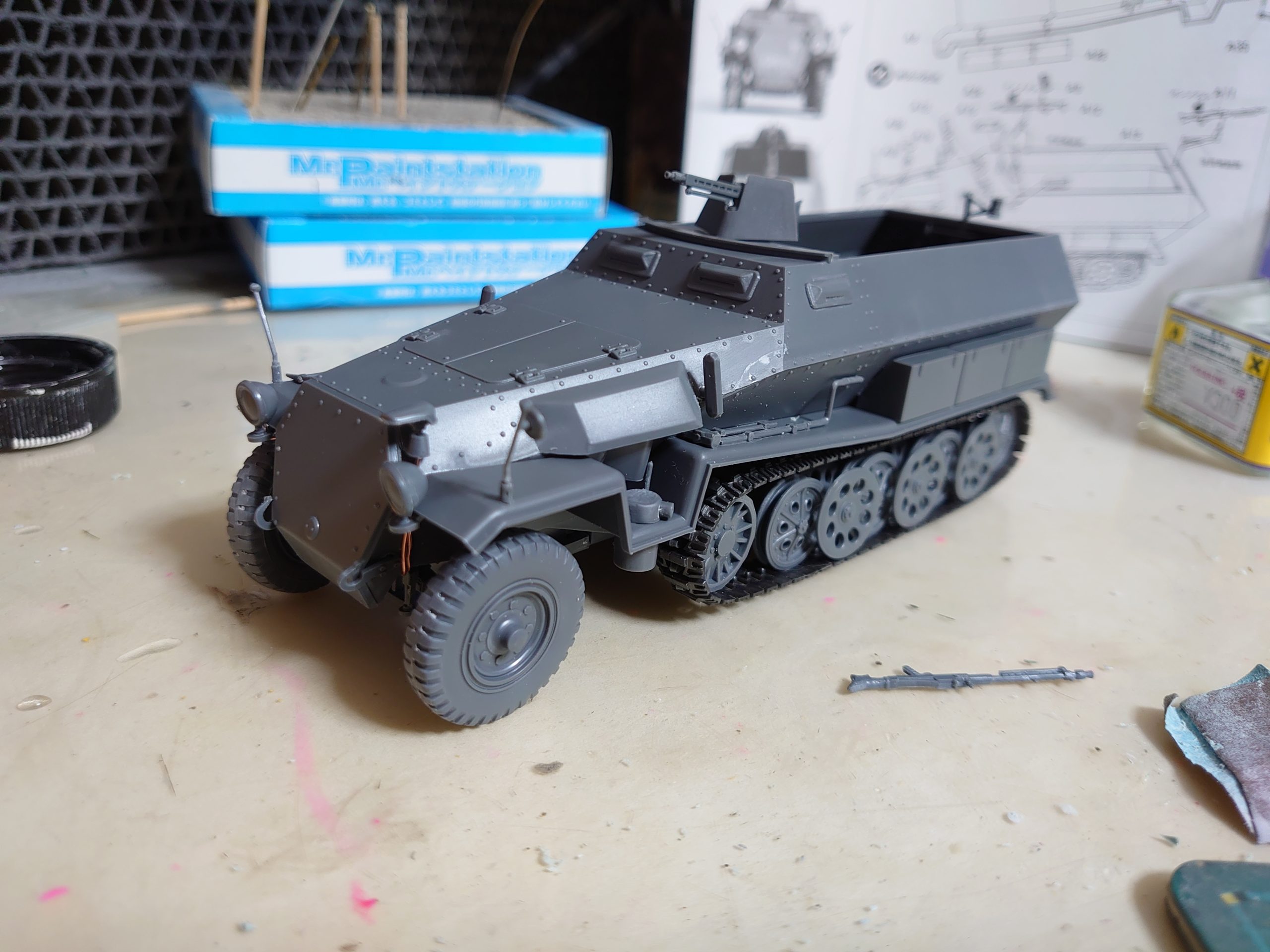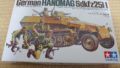タミヤMMシリーズの古参キット、ハノマーク兵員輸送車を作っていきます。

前回は内部パーツの組み立てで終わっていた。
今回はその続きとなる。

ヴァルダ殿、筆者がなにやら部品の補給に行きたがっているようですが。

頭のネジかな。

それは非売品ですよ。
足回りの組み立て
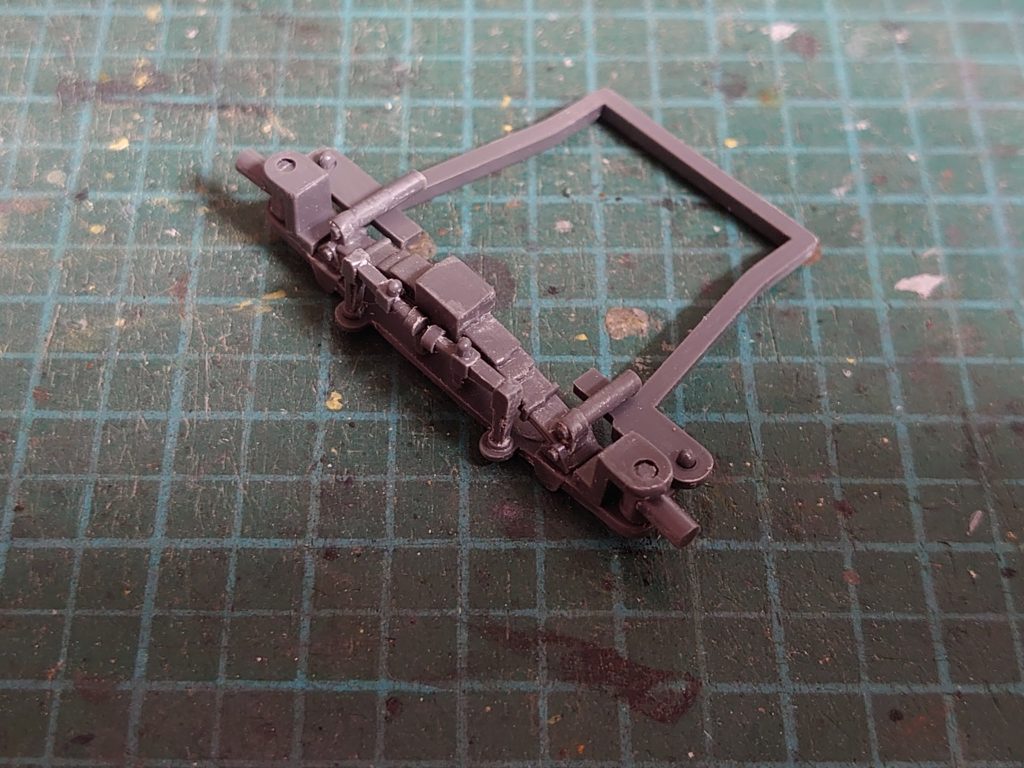

前回までは説明書の工程1~5番までを組み立てました。
今回は工程6番からです。
半装軌車特有の、履帯とタイヤで構成された足回りを組んでいきます。

まずは前部のタイヤ部分から。
フロントアクスルを組み立てる。
通常の装輪式車輌キット同様、ステアリングも出来る構造になっている。


その後はひっくり返して本体に取り付け。
タイヤは説明書ではこの時点で接着するよう指示が出ていますが、塗り分けや追加工作をする都合上、まだ接着はしません。


そのタイヤやその他車輪たちはこんな感じに。
タイヤはC6、C8 、C9パーツの3つで構成されている。
後者2パーツでC6パーツを挟み込むように組み立てる。
C6パーツは回転するので接着剤が流れ込まないように・・・・・・。

装軌式部分はティーガーやパンターのようなオーバーラップ式転輪となっています。
戦車に比べれば数は少ないので、落ち着いてゲート処理をしていきましょう。
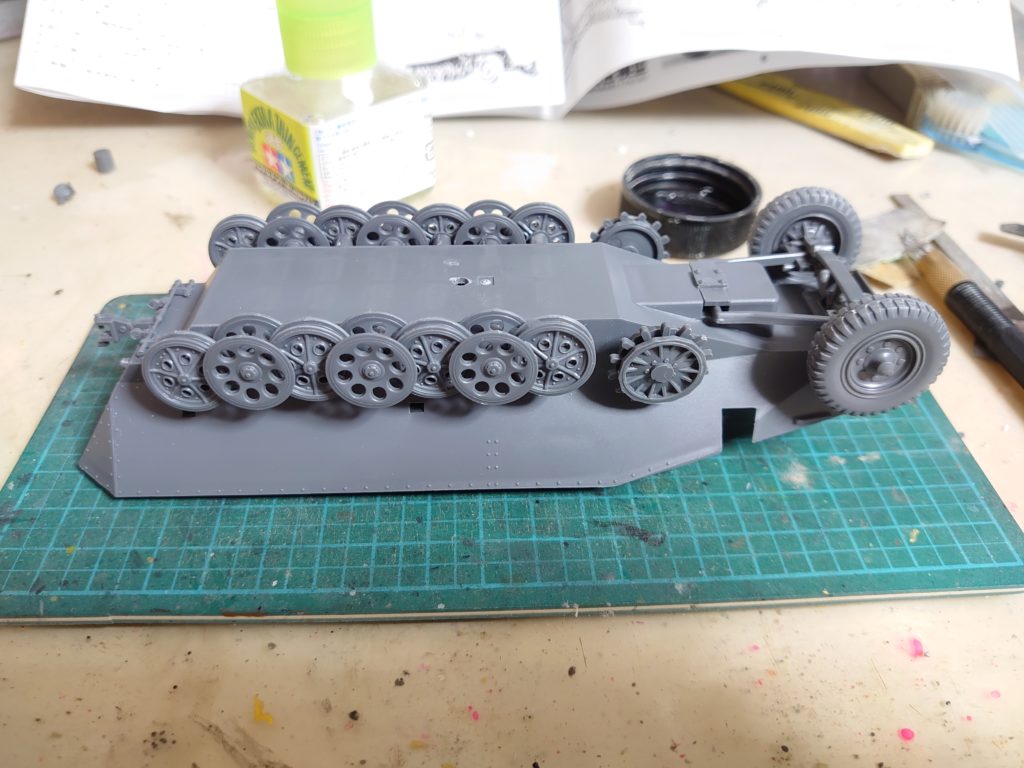

車輪類の取り付けです。
前述したとおりタイヤ部分は仮止めです。
同様に起動輪も履帯の調整があるため、ここでは仮止め状態です。

最近筆者は戦車類の転輪は「ロコ組み」で組んでいた。
けれど今回のハノマークは転輪が薄く、履帯との接地面積が狭く感じたので強度が不足すると判断。
そのまま転輪をサスペンションに接着してしまっている。
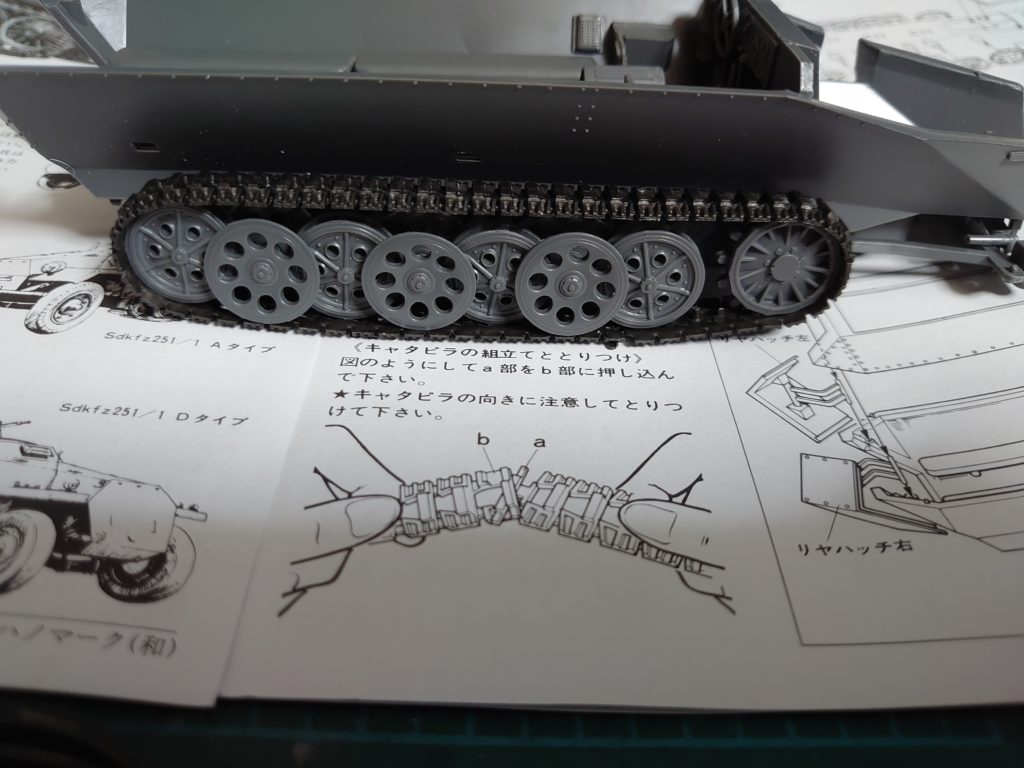

そして履帯はポリ製。
前回の記事でも触れましたが、両端のベロ部分を噛ませて接続するようになっています。

ポリ製なのでそのままでは接着剤や塗料が簡単に剥がれてしまう。
とりあえず後でプライマーを塗って解決しよう。
今ははめ込んで仮止めするだけにしておく。
車体上部の組み立て


車体後部に来るハッチ。
キットでは可動式となっています。
先に組み立てておきましょう。


似たような部品を組むので、車体上下パーツと共に仮組みして確認。
ここで下部側の後部に目立つパーティングラインを発見。
リヤハッチを組み込む前に整形しておこう。


準備が出来ましたらハッチのヒンジ部分を挟み込みつつ、車体の上下を接着します。
隙間が出来ないように、接着後テープで固定しておきます。

ただしテープを先に貼ってから接着剤を流し込まないように。
これをやるとテープ部分からあらぬところに接着剤が流れ込むことが。

リベット車体なので、表面が接着剤で荒れると面倒なことに……。


その後はフェンダーを接着します。
C型特有の独立した側面雑具箱と、一枚板の前面装甲が確認できますね。
この工程で付ける指示の前面ライトは後で手を加えるので、ここではまだ保留です。

筆者としては、車間表示灯(フェンダー前部にあるポール状のもの)等、細かい部品にはクレオスのMr.セメントSPがおススメのようだね。
狭い接着面積の部品も、がっちりくっついてくれるのだとか。
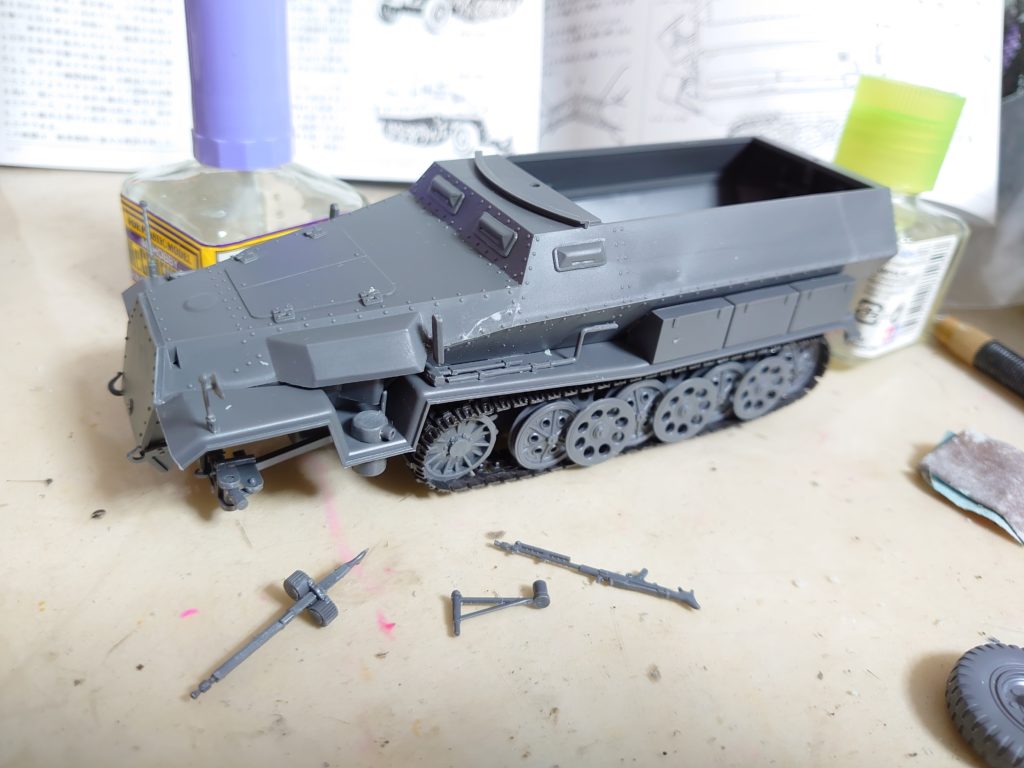

視察ハッチなど、更に細かい部品を取り付けます。
マシンガン類は塗装の塗り分けがあるので、接着はしません。

アホな筆者が流し込み接着剤で叩き割ったのか、車体左側に溶きパテでヒビを埋めたあとがあるね。
ライトコードの追加


キットのライトコードは省略されていますので、これを簡単な加工で再現してみます。
まずは箱絵を参考にライト下部と、基部に0.5mm径の穴を開けます。


コードはいつものエナメル線。
先にライト下部に接着。
コードをそのまま基部の穴に通しながら、基部とライトを接着。
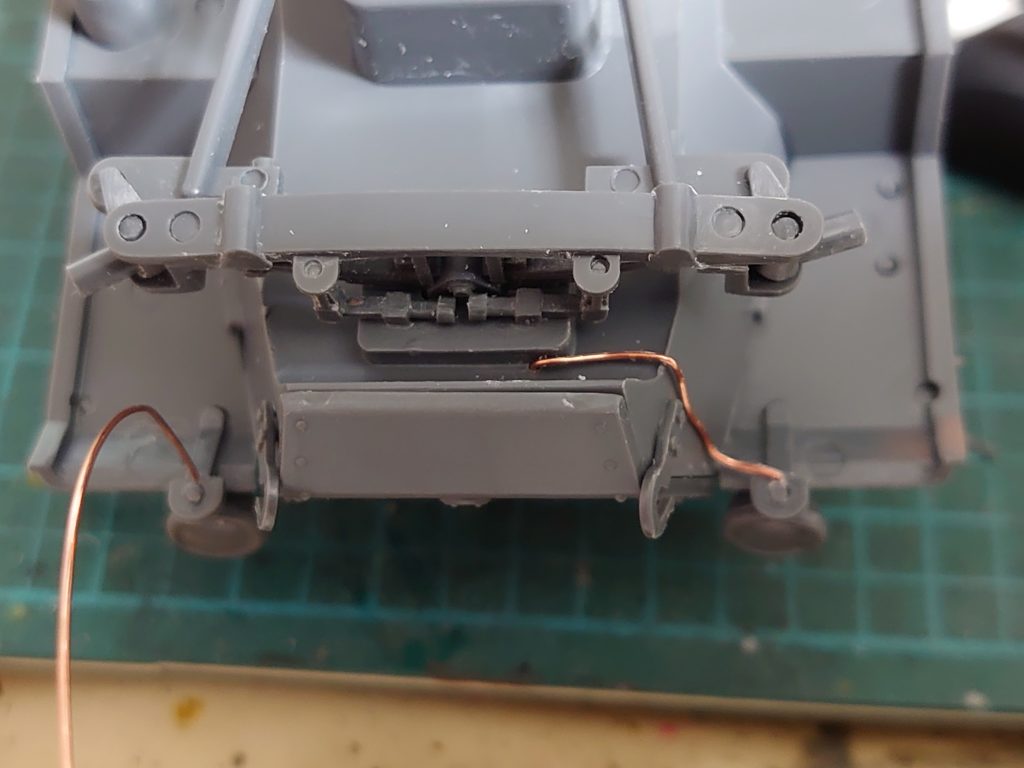

ライトはそのまま車体下部に流れていくけど……。
その先がどうなっているか調べてもわからなかった。
なので筆者は、車体下部に適当に穴を開けて通してしまっている。

ひっくり返さない限りは見えないのでこれでよいかと。
だれだって都合の悪いことは見えないようにしますし。
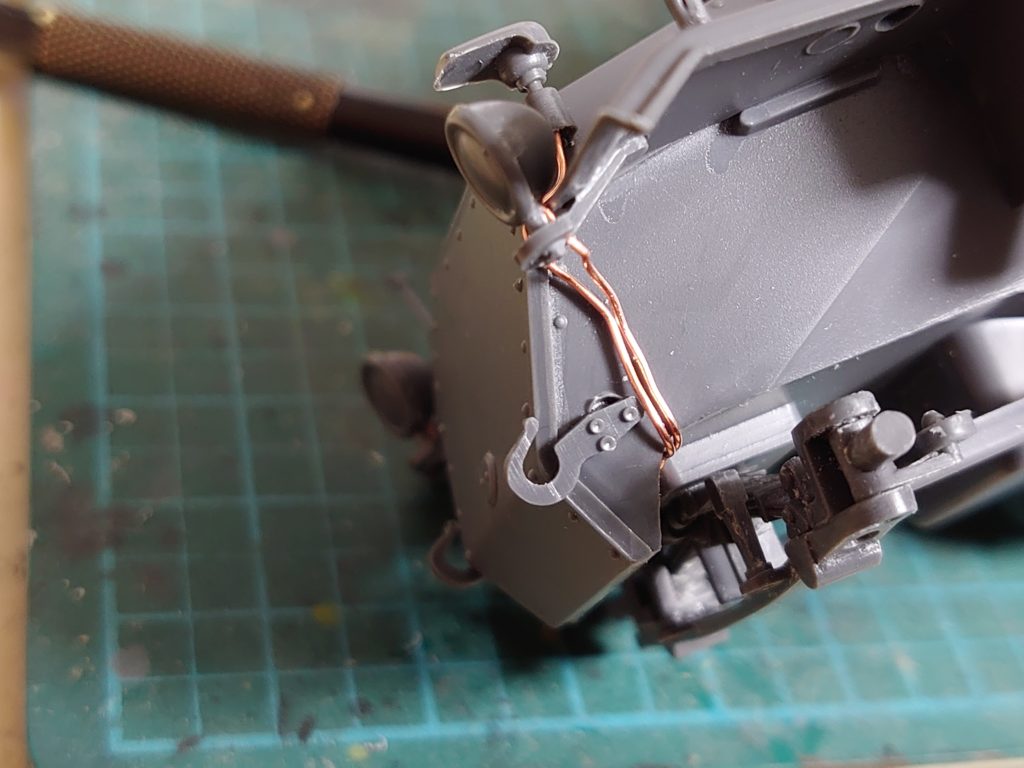

左側はノテックライトもつくので、同様にコードを作る。
やはり車体下部に穴を開けてコードの端を収めている。

コードはなるべく車体に合うようにしてください。
あんまり浮いているとタイヤに干渉するので……。
今回の戦果
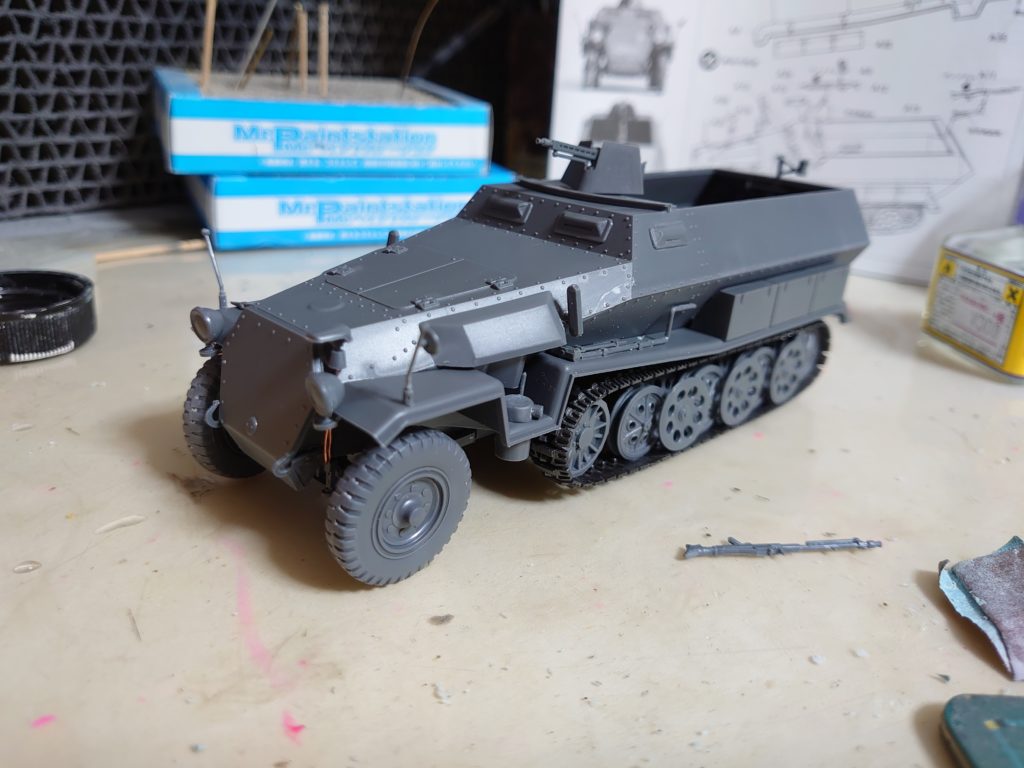

とりあえず、車体が組み上がったところで今回は中断しましょう。

塗装・・・・・・もそうだけど、付属する歩兵達の組み立ても必要になるね。
兵員輸送車としては、やはり外せないところ。
この記事で作っているキット
↓タミヤの公式オンラインショップはこちら↓